2021年の大河ドラマ・「青天を衝け」の主人公は渋沢栄一です。
栄一は日本企業の500の会社に関係していたといわれる人物です。
今回は渋沢栄一が残した『黄金の言葉』ともいえる、「論語と算盤」って
どんな本なのでしょうか?
この記事ではその著作を説明します。

これを読めば、論語と算盤の内容がばっちりわかるよ!
歴史好きになるきっかけや、青天を衝けを見るきっかけにしてください。
青天を衝け渋沢栄一の「論語と算盤」とはどんな本?
「論語と算盤」は永遠のベストセラー!
渋沢栄一の講演の口述をまとめたものとして、1916年に出版されました。
経済(算盤)と道徳(論語)という相反するものが、どちらも大切であると説いています。
経済の発展には道徳の裏打ちがないといけないと渋沢栄一は言っています。
この考え方は現代のSDGs(持続可能な開発目標)に通じる内容なのです。

時代を先取りしたような人だね!
渋沢栄一の論語と算盤は経済活動はこうあるべきと説いていて、時代を超えてベストセラーとなり、多くの人々に読み継がれています。
「論語と算盤」はどんな内容の本なの?
論語=道徳、算盤=経済の両立について書かれています。
そのどちらも大事にすることが大切であると言っています。
この本が出た当時は日本は経済が大きく発展していた好景気でした。
多くの人がビジネスで金もうけに走っていた時に、警鐘を鳴らすように出版されました。
「論語と算盤」はどんな人が読んでいる?
時代を超えて、幅広い著名人の間で読まれている「論語と算盤」。
現代では京セラ創業者・稲盛和夫氏、サントリーCEOの新浪剛史氏など、財界人のトップのひとたちが愛読しています。
またプロ野球選手の大谷翔平氏も読んでいるそうです。
「論語と算盤」の論語って何?
論語とは中国の思想家である孔子の行いや考えを孔子の死後に弟子たちがまとめた書物です。
512ある短文と長文が全10巻20篇に収められています。
紀元前5世紀ころに記されて、現代でも広く語り継がれ、日本には西暦390年ごろ伝わったとされています。
聖徳太子や徳川家康も政治の指南書としていました。

「子曰く(孔子先生がおっしゃるには~)」で文章が始まるのが特徴だよ
渋沢栄一「論語と算盤」の内容まるわかり紹介
日本の資本主義を作った渋沢栄一の口述をまとめた「論語と算盤」の内容をわかりやすくまとめてみました!

「論語と算盤は」10章からなるよ。
1章 処世と信条
この章ではお金儲けをすることは、悪いことではなく、お金を儲けて国を豊かに大きくすることは多くの人の幸せにできると言っています。
ただ、金もうけだけに走るのはいけない。大切なのは利益の追求という「算盤」的な考えと「論語」の道徳心をバランスよくやることが大切だと言っています。
この章の中で有名なフレーズと言えば
「蟹は甲羅に似せて穴を掘るというのが、私の主義だ」
蟹は自分の甲羅の大きさにあった穴を掘るという。自分の分をわきまえ、自分にできることだけをやるといくことです。
2章 立志と学問
何かを成すには自分から積極的に動かなくてはいけない。
成功を収めるためには、「志」を持つ必要があると言っています。
3章 常識と習慣
社会で生きていくうえで常識はとても重要なものです。常識とは言葉や行動が極端にかたよらず、善悪を見分ける能力のことと言っています。
この常識を身に着けるためには、「智・情・意」をバランスよく持つ必要があるといっています。
智とは、知恵、情とは情愛のこと、そして意は意志です。
知恵がなければ物事を見分けることができないが、それだけでは冷たい人間になってしまい、情愛がなければならないがこれは感情的なもので流されやすい。それを意志によってコントロールする。
意志だけでもまたただの頑固な者になってしまうので、この智・情・意のバランスが大切なのだと栄一は言っています。
4章 仁義と富貴
日本は古来からお金を稼ぐというのは卑しいことだという考えがあり、論語でも「道徳を大切にして利益を求めない」と説いています。
しかし栄一は孔子は本当は「道徳のない富ならば貧しいほうがましだが、道徳に基づいた利益ならば問題はない。」というのが本当に言いたかったことだと説いています。
利益を独占するのではなく、得た利益でよく使い、社会の経済を回すことで多くの人の幸せにつながるとこの章では言っています。
この章では
道徳に基づかない利益は長続きしない
このように言っています。
5章 理想と迷信
栄一は道徳を重んじて仕事をすることを説いていますがここでは、道徳も時代と共に変化するもので、本当にそれが道理にかなっているかを自分で考えることが大切だと言っています。
ただ、思いやりや親切などは時代が変わっても普遍的であるとも言っています。
6章 人格と修養
栄一は人を富や社会的地位などで評価せず、人格で人の価値を判断すべきだと言っています。
そして人格を高めるには日々自分を磨き続けること、理論ばかりにならないように現実の中で努力し知恵や道徳を身につけなければならないと言っています。
自分を磨けば、判断が正確に、かつ早くなる
このようにも言っているのです。
7章 算盤と権利
「論語」には、社会秩序を重んじて個人の主張を否定する風潮が強いとされてきましたが、栄一は「正しい道理に進むなら、あくまで自分の主張を通していい」と書かれていると言っています。
沢山の人々が経済を動かしている社会では、問題が生じたとき、法律だけで解決しようとするとぎすぎすしてしまう。
それより「思いやり」を持ってそれぞれの権利を尊重するべきだと説いています。
社会においてある程度の貧富の差が生じるのは当たり前のことで、良い競争は積極的にし、悪い競争はさけるべきだとも言っています。
8章 実業と士道
商売は武士道を重んじてもうまくいくはずがないと長年言われていましたが、栄一はそれは間違いだと言っています。
武士道に反して自分の利益ばかり追求していっても人々の支持は得られず、結局うまくいかなくなる。
利益追求の行き過ぎを防ぐためにも武士道は必要で、日本人が武士道を持っていきていけば決して世界にも負けることはないと栄一は主張しています。
9章 教育と情宣(じょうぎ)
この章では子供や若者への教育について触れています。
「論語」では親孝行を説いていますが、栄一はそれは親が子供に強制するようなものではなく、子供の志を邪魔せず、大きな心で見守っていれば、自然と親孝行つつながると説いています。
また若者の教育について目的意識もなく学問のために学問をしていたりしても社会に出ても役に立たない。
なんのために学ぶのか、社会に出たときにその学問をどう生かすということを考えて学ばなければいけないと栄一は言っています。
子供は母親の影響が大きいのだから、女性もきちんと教育を受けるべきだと説いています。
10章 成敗と運命
人の運命はある程度決まっていて、自分の運命がどうであろうと常に良心と思いやりの気持ちを持ち、仕事に誠実かつ一生懸命取り組むのが人の道だと栄一はいっています。
運命に一喜一憂せず、いつでも恭(礼儀正しくする)、敬(人を敬う)、信(人を信頼する)の3つを守っていればいい。それを「人事を尽くして天命を待つ」ということだといいます。
結果として、悪運が強くて成功する人や善人でも運が悪くて失敗する人もいる。
成功や失敗は人生のカスのようなもので、それよりも人としてどう生きたかというのことの方が大切だと説いています。

今の私たちの生き方にも通じることがたくさんありますね!
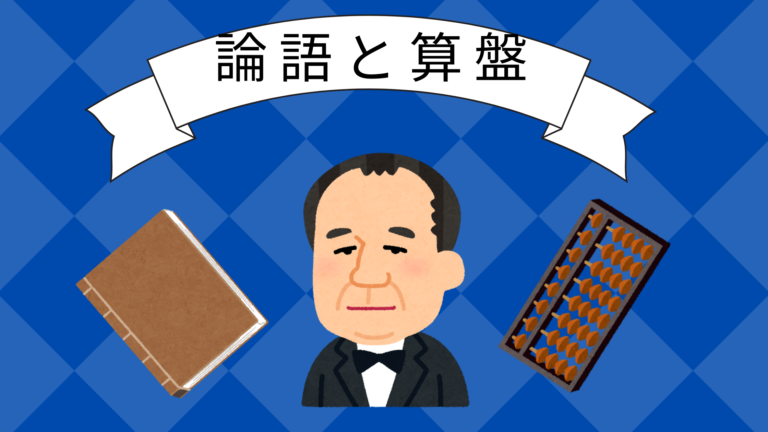


コメント